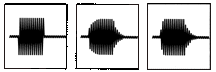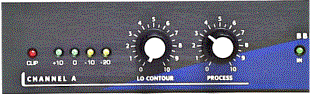輸入盤、ハイブリッド盤を買おう
すでにオーディオを趣味として久しいマニアなら、レコードの「輸入盤」は「国内盤」より音が良いことをご存じのはずだ。レコードのみならずCDですら「輸入盤」の音質は「国内盤」を凌いでいる。クラシックの多くはもちろん、海外POPSでも「日本語の解説」や「訳詞」が必要ないなら、「輸入盤」をお薦めする。その方が安くて音が良い。だが歌謡曲では「歌詞」がわからないと、音楽的感動の90%以上を捨てるようなものだから、英語が得意でない私は訳詞を得るためにまず「国内盤」を買い、それが気に入ったらさらに音質を求めて「輸入盤」を買足すことすらある。それほど「国内盤」と「輸入盤」の音は違う。
CDソフトには、「国内盤」と「輸入盤」だけではなく、SACDとCDが同時にプレスされた「ハイブリッド盤」が存在するが、このディスクが発売された当初はSACDプレーヤーが普及しておらず、私もSACDプレーヤーを所有していなかったため購入することはなかった。それに、SACDとCDが同時にプレスされていると聞いただけで「どっちつかずは音が悪い」と思い込むのがマニアの性でもある。 しかし最近になって「SACDの音質に気持ちが大きく傾いたこと」や個人的に好む「古いJ-POPのソフト」がハイブリッド盤化されて次々と発売されるようになり「SACDの音聞きたさ」にすでにCDで所有している音源をハイブリッド盤で買い直す機会が増えた。 せっかく買ったハイブリッド盤をわざわざCDプレーヤーで聴くことはまずないが、そこはやはりマニアの性?プロとしての興味?があり、CDとハイブリッド盤のCDレイヤーの音質を「CD専用プレーヤー」で聞き比べて驚いた!なんと「どっちつかずと思っていたハイブリッド盤」の音質が「CDだけがプレスされたディスク」よりも格段に音が良かったのだ。
仮にCDソフトを100とすると、ハイブリッド盤は120~150くらいの音が入っているように聞こえる。VICTORから発売されているXRCDという「高音質CDソフト」があるが、下手をするとそれよりもハイブリッド盤は音が良い。流行の「ノラ・ジョーンズ」もそうだったし「矢野顕子」や「南佳孝」も例外ではない。極端に言うなら、ハイブリッド盤のCDレイヤーの音は「SACDに近い」とさえ思えるのだ。
ハイブリッド盤の音がこんなに良いのなら、他にも気づいた人がいるに違いないと思って、所属するオーディオ関連のメイリングリストでこの情報の真偽を確かめたところ「Living Stereo/Living Presenceに関しては全数ハイブリッド盤の方が良かった」という情報や、逆に「Boston・More than a feelingはCDに軍配が上がった」などという興味深い情報が数多く寄せられたが、おおむね好意的な意見が多かったように思う。
ハイブリッド盤のCDレイヤーの音質がCDと異なる原因は定かではない。単なる憶測にすぎないが「SACD盤はCD盤よりも高精度な機械でプレスされているためCDレイヤーの精度が高い」ことによるのかも知れないし、より信憑性の高い話だと「SACD制作時にDSDリマスターからPCMに変換されてCD層が作られる」ことが多いから「マスタリングの違いによる音の差が大きい」と言う説もある。いずれにしても「ハイブリッド盤の価格がCDソフト並みに安くなったこと」もあり、今後ソフトを購入する時には「SACDプレーヤーを所有していない」場合でも、とりあえずハイブリッド盤を購入して損はないと思われる。
少し話は逸れるが、最近「マスタークロック」を高精度にすると「CDがSACD並になった」あるいは「SACDはもう要らない」などと、声高に宣伝している雑誌やショップがあるが感心しない。上記のような聞き比べを行って、ハイブリッド盤のCDレイヤーの音質がSACDに近いと感じても、その後で「本物のSACD」を聞くと、やはりその違いに愕然とする。SACDとCDを比べて悦に入る人達は、きっと「本物のSACDの良さを知らないだけ」なのだろうと思う。
「良い音」の基準
メイリングリストは、この「ハイブリッド盤とCDの音の違い」で火がついて、それまで皆が感じていた「CDに対する不満」が続出した。それに対し「CDで問題なしとする反対意見」も熱く交わされた。中に非常に興味深く、参考になる意見が多数あった。私なりにそれらの要点をまとめてみよう。
ほとんどのオーディオマニアは、「音質のさらなる向上」を望んでいる。しかし今回の討論で、実はこの「良い音の基準」が人によって思った以上に「違いが大きい」ことを再認識させられる結果となった。
すでに過去に発行したDMに掲載したが「人種」によって「良い音の基準」が異なるのは「地域による言語周波数の違い」や「宗教と結びつく音楽の違い」などから、ある程度合理的な説明が可能だ。しかし、今回の討論で同じ日本人でも人による「良い音の基準」の違いが非常に大きいことを知った。その違いを今までは、単なる「好みの差」で片づけていたが、今回の討論で「好みの差が生じる一定の論理がそこにあるのではないか?」と思い当たることがあった。
「良い音の基準」をリスナー側からまとめると意見は二つに収束する。ひとつは「演奏者が出す音を基準とする聴き方」であり、他方は「聴衆が聴く音を基準とする聴き方」である。「演奏者を基準」に求める良い音は、「楽器から出たそのままの音」であり、再生には一切の濁りや響きの付加が許されず、限りなく高い純度が要求される。それを成し遂げるためには、楽器から出た音を寸分違わず全て正確に再現する必要があるから、装置の中での「不要な音の発生による着色」や「リスニングルームの反射による混濁」などは「音の純度が低下する=音を濁らせる」原因となるので極力排除せねばならない。ある意味では「ヘッドホンで音楽をモニターするのに近い聴き方」だと思う。他方、「聴衆の基準」で求める良い音は、適度な響きを含む「もっとリラックスした音」である。言い換えれば、原音よりも「雰囲気重視」の音である。鋭すぎる音や、あまりにも純度の高すぎる再生音は、聞き手に「過度な緊張感」を生じさせ雰囲気を損なってしまうから、再生時に収録されていない適度なエコー感と混濁感が加わっても差し支えない。純度はそれほど追求しないから、緊張しない程度の音質でバランス良く、雰囲気を楽しめればそれで良いというのが「彼らの求める音」である。
両立は難しい
この二つの聴き方はまるで正反対だ。生演奏ならまだしも「オーディオ機器では、決して両立させることが出来ないパラドクスを含んでいる」と私は思う。その理由をオーディオの技術的側面から説明しよう。
「演奏者の基準」で良い音を出そうとすれば「音のエッジ(楽器のアタック)」は、限りなく鮮明でなければならない。マイクが捉えた音をそのまま再現するためには、システムは何よりも「過渡特性の良さ」を要求される。「楽器と同じ音」を得ようとすれば、システムの「反応速度(応答性)」を限界まで上げなければならない。過渡特性の向上はアンプに求められる最大の課題である。しかし、それを成し遂げるために一般的に「再生上限周波数」を上げればよいと考えられているようだが、それは一部正しく、そして他方では明らかな間違いである。なぜならば「測定上の再生上限周波数」は「正弦波(同じ信号の繰り返し)」を再現する性能であって「楽器が発しているようなパルス波(繰り返しのない高周波信号)」の再現性を保証していないからだ。
一方、電気信号を音に変換する「スピーカーの高音部」にも大きな問題がある。スピーカーは「ツィーターという薄い膜を往復運動」させることで高音を発生するが、楽器にはスピーカーのツィーター(高音発生ユニット)のような「薄い膜」はない。同じ高音を発生するのにもかかわらず、スピーカーと楽器の外観はまるで違うのだ。実際、「スピーカーと楽器から高音が発生する原理」はまったく異なっている。 楽器が高音を発生するときは、その表面(振動体)が「さざ波のような運動(振動)」を行うが、これを「波動モーション」と呼ぶ。「波動モーション」による高音の発生時には「十分に強度の高い振動体」が「小さな面積(体積)の空気」を「強力に圧縮する」ため、空気の「粘り」に打ち勝ってそれを強く圧縮する力が得られる。つまり、楽器のような「強度の高い振動体」が「波動モーション」で振動すると、振動体の周囲にある空気は「高速で圧縮」され「非常に圧力の高いパルス状の音波(高調波)」が発生するのだ。
しかし、ツィーターのように「強度の低い振動体(薄い膜)」を「往復運動」させ、一度に大きな面積(体積)の空気を一度に圧縮する方法では、そのような「強力な圧縮」は得られないから、楽器が発生するような「圧力の高いパルス状の音波」が得られない。楽器とスピーカーでは、同じ高音でも「音の質」が違うのだ。
スピーカーの音を少しでも楽器に近づけるために「ユニットの圧縮力を逃がさないホーン型ユニット」のような工夫が必要になる。しかし、ホーン型ユニットでは「指向性が狭くなる」という問題が生じるなど、完全な問題の解決にはならず、どこまで行ってもスピーカーから楽器と同じ音が出るとは思えない。
さらにスピーカーから出た音は空気の「バネ性」により、リスナーに届くまでに「高域が距離に比例して減衰」してしまうから、スピーカーから離れれば離れるほど「高域の明瞭度」が損なわれてしまう。試しにスピーカーにうんと近づいて音を聴くと良い。驚くほど明瞭で輪郭のハッキリした音が聞けるはずだが、スピーカーから離れると高域はどんどん不明瞭になる。
しかし楽器の音は、距離を離れて聞いてもスピーカーよりも明らかに高域の減衰が少なく明瞭度が低下しない。ツィーターが発生する「圧力の低い高音」に比べて、楽器が発生する高音には、先ほど説明した「圧力の高いパルス性の高調波」がたっぷり含まれているからである。この「高調波」の「質と量」がスピーカーの音を「生の音」に近づける「鍵」となる。
スピーカーの音を生音に近づける方法
スピーカーが「パルス成分の少ないなまった高音」しか発生しないなら、「スピーカーの再生音を原音に近づける」ためには「マイクが捉えた音よりもパルス成分(楽音の輪郭/隈取り成分)を強めに発生させればよい」と推察できる。つまり「減衰する分をあらかじめ補ってやる」と言う考え方だ。事実、楽器の「近接した距離で聞く音が主体で構成されるJAZZ」の再生では、より明確な音が求められるので、輪郭が強調されるJBL製品などが珍重されている。この「強調」を電気回路で行うのが「BBEプロセッサー」だ。この装置を使えば「楽器との距離感」を文字通り「自由自在」に調整できる。また、BBEの仕組みを知ることは「CDでJAZZやPOPSをより心地よく良く聴くための音作り」の大きなヒントになる。
BBEプロセッサーの仕組み(BBEのホームページより抜粋)
BBE回路(特許取得済)は、ラウドスピーカーの問題点といわれるスピーカーコイルによる高周波での交流抵抗のズレと誤差を補正します。つまり交流抵抗により減衰した高域とその時間遅れによるラウドスピーカーの不自然さを補正しライブ演奏に近い音を得ようとするものです。
BBEのプロセスはまず入力信号をチェックして、衰退した高周波をレベルアップします。そして中域・低域を高域に比較して遅らせることにより、聞き手に高・中・低波が同時に届くように調整します。これは大変重要なことで、生演奏を聞くのと同じ音に近づけるわけです。鮮明さ、音のきめ細かさ、存在感、鋭敏さ、そしてニュアンスが驚くほどはっきりと出てきます。そのため、BBEは「オーディオのオートフォーカス」とも言われ、米国のオーディオ誌は「すばらしいプロセスだ。どんな音楽にも使えて、高域の鮮明さと伸びがよい。自然の音をそのまま再現する大変優秀な機器である。」とコメントしています。
高調波と基本波の時間的関係の重要性
この説明だけではBBEプロセスを理解するのは難しい。もう少し詳しくわかりやすく解説すると、次のようになる。私達が自然界で聞く音(物理現象によって発生する音、アコースティックな楽器の音がそれに該当するが、電気楽器は、物理的に発生しないので含まれない)は、常に基本波(サインウェーブ)とそれぞれの音に特有な高調波成分(前述したパルス波)から構成されている。ほとんどの高調波は基本波より先に届き、若干の残りが基本波より後に届く。例えばドラムをスティックで叩いた場合、スティックがドラムに当たった瞬間、ドラムの皮の表面が分割共振(波動モーションで振動)を起こし高調波からなるノイズが発生する。そして、しばらくしてからスキン(皮)がゆっくりとした往復振動を始めるが、このスキン全体のゆっくりした動きが基本波を形成する。
このようにして発生した音は、その一粒一粒が高調波と基本波の時間的関係を保ちながらリスナーに届く。(これは極端にモデル化した説明で、実際の音はきわめて複雑な構造になっている)そして、ドラムから出た音が人間の耳に届くと、脳は音の解析を始めるが、この時に脳は音の始めの部分(高調波)が入ってくるとすぐに解析を始め、その直後に入ってきた後半の部分(基本波)はマスクされて(切り捨てられて)耳には届いても聞こえにくくなっている。この「最初に耳に入った高調波から音を分析する」という仕組みは、人間が進化してきた過程で我々の脳が音を効率よく分析できるように進化した結果である。
高調波と基本波の関係を具体的に説明しよう。
基本波は単に音の高さ(音程)を決めるサイン波なのに対し、高調波は音の音色を決める重要な情報を含んでいる。この高調波の含まれ方によって私達はその音が何の音であるかを判断している。例えば同じピアノの音でも、その高調波の含まれ方によってピアノの種類まで判別が可能だし、他の楽器や人の声、物が壊れる音なども同様のプロセスで聞き分けが行われている。
これを実験で確かめるには、楽器の音を録音したテープを逆回しで再生すれば良い。テープを逆回しにすると音程は変わらないのに、楽器の種類は判別できなくなり、ピアノの音はオルガンのように聞こえる。これは、高調波が基本波よりも遅れる(高調波と基本波の時間的関係が逆転する)ことによって、音色が判別できなくなるためで、高調波が音の聞き分けに非常に重要だという証明だ。
この高調波とは、いわゆる音楽用語で「アタック」と呼ばれる成分で、楽器の音の出始めから1/1000~2/100秒の時間帯に多く含まれている。しかし、自然界の音をマイクで録り、イコライザーやフィルターを通したり、増幅アンプを通しスピーカーを鳴らす過程(空気のバネ性による減衰など)で一般的に高域が遅れ、それに伴ってそこに含まれる高調波も遅れてしまう。このように録音-再生のプロセスでは、多くの場合基本波より高調波が遅れてしまうので、人間の脳は先に届いたあまり重要でない基本波を分析し、遅れて届いた重要な高調波を無視してしまう結果となる。そうなると音の明瞭度が極端に悪化してしまう。これらの理由から、スピーカーを含め周波数特性がいくらフラットであっても、高域に遅れがあると高調波が十分に耳に届かず、明瞭度が悪化することになる。結果として、オーディオ装置により再現される音楽は、アタックの再現が不十分となって、生音がいわゆるオーディオ的な音になったり、電気臭く感じられたりしてしまう。 この失われたアタックを物理的に補助し、通常のスピーカーでは再生できない高調波を再現する目的で作られた補助ツィーターが「AIRBOW CLT-2」や「CLT-THEATER」という、波動モーションで高音を発生するツィーターであり、この高調波の遅れを電気的に補正する目的で作られたプロセッサーがBBEなのだ。
BBEプロセッサーは、先ほど述べた「不可避に発生する高域の減衰や損失をあらかじめ電気的に補正する」働きを持つ。この仕組みを「BBEプロセス」と呼び、BBE社が特許を取得している。BBEのプロセスにはいくつかのバージョンがあり、今回紹介するBBEのモデル482Iには、「BBE/PROプロセス」が採用されている。この「BBE/PROプロセス」を採用している「482I」は、従来のBBEプロセッサーに比べ効果が著しく改善され、プロセッサーを使用したときの悪影響(解像度の低下や音の濁りの発生)も、ほとんど無視できるレベルにまで減少している。この「BBEプロセス」をさらに詳しく説明しよう。
BBEプロセス
一般的には、減衰した高域とその明瞭度を回復するためにトーンコントロールやイコライザーで高域をブーストするわけだが、音がきつくなるなど「副作用」が強く正しい方法とは言えない。こういった問題を理論的に解決するために、基本波に対して遅れた高調波成分を基本波の前に移動し、波形を自然界の音と同じ構成とし、次に減衰しやすい高域を若干ブーストする事により、より自然に明瞭度を回復させようとするのがBBEプロセスの基本技術である。
BBEはまず音声周波数を3つの周波数バンドに分割し、150Hz以下を低域、150Hz~2.5KHzを中域、2.5KHz以上を高域とする。この中域と高域に高調波が含まれる。低域は、パッシブなローパスフィルターで約2.5msほど遅らせ、中域はアクティブなバンドパスフィルターで0.5msほど遅らせる。これらの遅延は周波数に反比例したリニアーなもので、高域には遅れを加えないため相対的に低域中域に比べ進む結果となる。次に高域の信号をリファレンスとして、中域と高域の信号を比較しながら連続で相対的な高調波の比率を検出し、高域の増幅レベルを可変することで、減衰する高調波を正確に補正出力する。このプロセスがBBEの基本原理である。
このBBEプロセスにより、高調波の位置と振幅が回復することで、低域が物足りなく聞こえる場合があるが、そのバランスを取るために50Hz以下の低域を連続的にブーストできるようになっている。つまり、低域と高域のレベル可変・トーンコントロールと、中低域の遅延回路が一体となった装置と考えても差し支えない。
このようにBBEは、通常のトーンコントロール回路とは異なり、スピーカーやケーブル、回路などで遅延する高域をあらかじめ進めておくことで明瞭度改善効果が高く、位相乱れの少ないスッキリした音質が得られるのが特徴だ。BBEプロセスでは、位相補正と高域ブーストの効果で、イコライザーのように単にブーストを行う場合に比べ、約半分のブーストで同じ明瞭度が得られる。プロ用BBEは、これまでに10万台以上が世界中で販売され、様々な音楽シーンで用いられている。また家庭用TVの音声回路の明瞭度向上にも、BBEは多く用いられている。 今回紹介するBBEの「MODEL482I」は、2Chの独立したBBE・PROプロセス回路を持ち、入出力はRCAと1/4”フォン(アンバランス)がそれぞれ1系統ある。入力レベルは固定、出力レベルは各Ch毎に低域(ローブースト)と高域(BBEプロセス)がそれぞれ連続可変で装備されている。
上位機種の「MODEL882I」には、XLR(バランス・2番ホット)と1/4“ステレオフォン(バランス・チップホット)各1系統の入出力があり、バランス回路となっているが、基本回路や調整機構、アンバランスで作動させたときの音質は482とほぼ同等だ。 これらのモデルの下位に、BBEⅡプロセスを搭載したシリーズが用意されているが、BBE・PROプロセス搭載モデルと比較して音の粒子が粗く、ざらついた感じでハイエンドコンポーネントとの組合せではちょっと苦しい。プロセスの世代としてもPROプロセスが新しく、あらゆる意味で完成度が高い。
MODEL 882Iの入出力端子。
XLR(バランス・2番ホット)と1/4“ステレオフォン(バランス・チップホット)左右独立で各1系統。
実際にこの装置を繋いだときの音質だが、BBEプロセスの量を多くすれば、直接音の成分(エネルギー)が強くなって、子音の強調感が高まる。BBEプロセスの量と、リスナーと楽器の距離が正比例して近づく感じだ。 BBEプロセスの量を増やすと高域がやや持ち上がって聞こえるので、それを補正するために低域をブーストする。しかし、調子に乗って「BBEプロセス」と「ローブースト」を強くし過ぎると、音の粒子が粗くなり、極度のドンシャリの音になるから注意が必要だ。ほとんどのディスクでは、BBEプロセスのボリュームが9-12時、バスブーストのボリュームが最小-9時くらいで、ウェルバランスとなるようだ。ブースト量の調整は、慣れると難しくないが、最初は強くし過ぎないように注意するのがポイントのようだ。
ローブーストとBBEプロセスのボリューム。 入出力は、左右独立の2系統。写真のダイヤルの位置は、ボーカルなどで良かったポジション。
BBEの効果
BBEを使用すると、音楽的にかなりドラスティックな変化がおきる。JAZZで強めにブーストを効かせれば、シンバルの音が宙を飛び、トランペットがつんざくように空気を切り裂くような明瞭度が容易に得られる。ボーカルでほんの少しブーストを使えば、ニュアンスや気配が深まり、唇の濡れ具合までをコントロールすることが可能となる。クラシックでは適切な量のブーストを加えると、デジタルの大きな不満点であるバイオリンの高域を鈍らせずに、さらに鮮烈にすると同時に弦の硬さが取れる。ブーストが上手くはまるとスピーカーが楽器に変貌するほどの大きな効果があらわれ、従来再生をあきらめていたソフトでも、BBEプロセッサーを使えば楽しく聞けるようになることすら夢ではない。
Century;mso-hansi-font-family:Century;background:white’>だがBBEプロセッサーの一番の利点は、エフェクト量が「無段階可変」であるということだ。この可変機構を有効に使えば、システムの変更無しにリスニングポジションと楽器の距離感を無段階で調整できることが可能になるのはもちろんのこと、「録音に合わせて自分の好みに音をチューンする」、「再生音量に応じてラウドネス機構のように使用する」など、まさに自由自在にスピーカーから出す音の「明瞭度」をコントロールできるようになる。
この装置との組合せて最良の効果を発揮するのが、1BIT系のデジタル機器、コンデンサー型スピーカーなどの正弦波の再現性には優れるが「高調波成分(アタック成分)」の再生が難しい機器だ。なかでも「AIRBOWのCH7700SuPER2」との組合せは抜群で、柔らかく柔軟な音質から鋭く鮮烈な音質までCDプレーヤーの音を無段階に変化させることが出来るようになると共に、1BIT特有の音の芯の弱さを補い、しっかりさせることも可能となる。しかし、価格の安さから憂慮される音の濁りの発生や、解像度の低下はほとんどない。
BBEの説明による「高調波と基本波の関係の重要性」が理解できれば、「楽器から出る音を直接聞くための音作り」のヒントは十分得られると思う。乱暴に言えば「高調波の質(パルス成分の正確な再現)」と「高調波と基本波の時間的関係(経験によると1/10000秒以下のオーダーまで重要)」をきちんとすればよいと言うことである。
このように「BBEプロセス」は、感覚に頼っていた「オーディオの音作り」を一部ではあるが「科学的に解明」し「論理的にそれを成し遂げることを可能とした」画期的な装置である。その理論から学べることは非常に多い。
直接音と間接音の関係
次は、クラシックのような「広いホールで演奏される音楽」を「楽器から離れた場所で聞く」場合を考えてみよう。一般的に誤解されがちなので注意して欲しいのだが、私たちがリスニングポジションで聞いている音の半分以上、最大で80%近くまでの音は「スピーカーから直接出た音ではない」のだ。ではそれらの音がどこから出ているかというと「壁や天井、床から反射してリスナーに届く音」なのだ。例えると、壁からの反射が全くない部屋(あるいは戸外)で電球を一つ点けても部屋は明るくならないが、この電球に笠を付け、壁を白く塗って電球の光を反射させると部屋は一気に明るくなる。このときの電球をスピーカーに、部屋の明るさを音量に当てはめて考えると、スピーカーの「直接音」と「反射音」の関係とその量的な割合が理解できる。
リスニングルームの影響
もちろんスピーカーから発生する音にも「ホールの間接音」は含まれている。しかし、心地よい音の広がりを得るためには、それだけでは足りないから、部屋の反射音を調整して「擬似的にホールトーン」を作り出し、それを補う作業が重要になる。スピーカーを設置する部屋は、オーディオ専用ルームではない場合がほとんどだ。そのためスピーカーを「理想的な位置に設置できない」・「音を大きくできない」など多くの制約が考えられる。しかし、それでもリスニングルームの音響特性を把握し、問題点に対処しながら設置を行えば「スピーカーの価格が一桁上がった」と感じられる程、大きな音質の向上を得ることができるだろう。
無論、リスニングルームで生じる「残響音(反射音)」は、元々は収録されていない音なので、多すぎるとやはり音楽を作り替える、透明感を損ねるなど、悪影響を及ぼす。しかし消しすぎると、音楽の「艶」や「潤い」、「広がり」などを殺ぎ、音楽を心地よく聴けなくしてしまう。調整の詳細は、冊子の「裏面」に詳しく記載している。
サラウンドの薦め
このリスニングルームの影響や難しいセッティングを「一気に解決する裏技」が「サラウンド」である。サラウンドでは「機器の設定」によって「電気的に反射音をコントロール」することが可能だから、ある意味では「部屋を丸ごと作り替えるに等しい音響の変化」を一気にもたらすことが出来る。
また、部屋の大きさにかかわらず「大きな部屋で起きた反射音と同じ状況の反射音」を作り出すことが出来るので「狭い部屋でも音場を大きく展開する」ことが可能となる。更に、部屋の音響を整えるために準備しなければならない「パネル類のコスト」を考えれば、出来のよいAVアンプと小型スピーカーに投資する方が「返って安く付く」ことすらある。「最大の利点」は「部屋の美観を損ねない」ことだ。お洒落な小型スピーカーを利用すれば、場所も取らないし、美観を損ねたとしてもそれは最小限にとどまる。リビングで音楽を心地よく聴きたいとお考えの場合、サラウンドを抜きにしては考えられない。それほど最近のサラウンドは、進歩している。
音量の問題
余り考慮されないが気を付けて欲しいのが、スピーカーの音量による「直接音」と「間接音」のバランスの変化である。「直接音」は、音量に正比例して増加減少するが、「反射音」は、正比例よりもやや大きな比例関係で「増加する傾向」があり、音量が大きくなるに伴って「反射音の割合が大きく」なる。
それは、ホールトーンを多く含むディスクを「音量だけ変えて聞いてみる」とよく分かる。最初は「間接音が少なすぎて」、寂しい音で広がりも足りないが、音量を上げるに伴って音数が増え、音場の広がりも大きくなる。しかし「ある一定音量」を越えると、逆に音が濁り始め音場も広がりにくくなってしまう。これは「人間が聞き取れる音量に下限がある」ことが原因(音量を下げると音量の小さな間接音から先に聞き取れなくなる)だ。
つまり、「小音量で聞くことが多い場合」には「部屋をライブ気味」にして「間接音を多く」し、「大音量で聞くことが多い場合」には「部屋をデット気味」にして「間接音の発生を抑える」ことが理に適う。
天井と床の反射の影響
見落とされがちなので注意して欲しいが、最も大きな「反射音」は「壁からでなく天井と床の反射」により生じている。なぜなら、リスニングルームでは「天井と床が最も大きい平行面」でなおかつ障害物も少ないから、影響が甚大なのだ。この平行面による「フラッタエコー(反射を繰り返すエコー)の発生」を防ぐため、スピーカーを設置するときに床や天井から十分に離さなければならない。小型スピーカーを床に直に置く(マルチチャンネルシステムではエフェクトスピーカーを天井に付ける)などということは絶対に避けなければいけない最も悪い例である。
床がフローリングの場合表面が硬く、大きな反射が避けられないから、スピーカーの直前の床部分に「毛足の長い絨毯(理想はムートン)」や「厚めのマットレス(表面は起毛)」などを敷き吸音を行えば、音質の改善に非常に大きな効果がある。できれば天井にも吸音を行いたいところだが、実際問題としては難しいので、その分「床の吸音を入念に行う」ことで効果を補わねばならないから、床一面に絨毯を敷き詰めても過剰ではない。
スピーカー背後と左右の壁からの反射を調整する
さらにスピーカーの背後の壁が「ビニールの壁紙」や「ガラス」・「金属」・「平面性の高いプラスティック」などで構成されていると不愉快な反射を引き起こすことが多いので、そのような恐れが感じられる場合には、カーテンなどで吸音を行う方と良い。使用するカーテンは、できれば天然素材の「綿」・「絹」・「羊毛」が好ましく、合成素材なら「ポリプロピレン・ポリエチレン」などの材質が適し「アクリル」は適さない。
スピーカーの左右の壁で特に影響が大きいのは、スピーカーよりリスナー側に位置する部分である。このような箇所には、やはりしっかり吸音を行いたいが、その前にスピーカーを十分に内側に向けて設置するなど、影響の低減を試みてからでも遅くはない。また、インテリアやその他の事情で、どうしてもカーテンや吸音材の設置が難しい場合には、スピーカーを壁から45度以上の角度をつけて大きく内側に向けることで影響を低減することができるかも知れない。吸音材を使用する場合には「KRIPTON AP10」が最も優れた効果を発揮する。
リスナー背後の壁からの影響
スピーカー背後と左右の壁の影響と対策の次に、リスナー背後の壁からの反射の影響を考慮する。耳の後ろに手を当てて音を聴けば、音がまったく違って聴こえるのがわかるはずだが「リスナーの直後(1M以内)」に壁がある場合、背後の壁からの反射は非常に有害なことがある。できればリスニングポジションを壁から離せれば理想だが、それが不可能な場合には背後の壁に吸音措置を施す方が良いだろう。
低音の処理
ここまでは、主に中高音域のルームチューンの説明をしてきたが、低音域のチューニングも忘れてはいけない。中高音(200Hz~500Hz以上の周波数)が「光が反射するような動き」をするのに対し、低音は「壁や床にそって流れる」ように進む。また、中高音が音の広がりや音像の定位感に大きな影響を及ぼすのに対し、低音は音の広がりを濁らし、低音部と中高音部の分離感を損ねる、中高音部の明瞭度を低下させる、音を曇らせる、などの悪影響を及ぼす。
周波数が低いため「低音発生源の位置(サブウーファーの設置位置)」は、まったく考慮されないことがほとんどであるが、低音域の共鳴や伝送の乱れは「スピーカーと壁の距離」に大きな関連性があり、実はその距離が㎝単位で変わるだけでも低域の音響特性は大きく変化するのだ。 低音域の反射で最も大きな問題が「左右からの低音の回り込み」である。右側に設置したスピーカーから出た低音がスピーカーの背後→中央の壁と壁面を伝わりながら、左側の壁へと流れ、リスナーの左側から聴こえるようになると、左側のスピーカーの低音と右側のスピーカーの低音が混ざって音場空間を大きく濁らせてしまう。(反対側も同様)。これを改善するには、スピーカーの背後の壁沿いに、低音の流れを遮る形で吸音パネルを設置することで対処できる。パネルを設置しない場合は、ラックなどを障害にすることでも効果があるが、表面の硬いラックでは、低音が反射するのでラックの横に「吸音措置」をとると外観を損ねず音も良くなり「一石二鳥」となる。
スピーカーのウーファーと床との距離が近づきすぎると、ウーファーから放射された低音が、すぐ近くの床を伝わって這うように進み、リスナーにやや遅れて届くため、「低音の量感」は増すものの「かぶり気味の濁った低音」が「低音楽器の音階を不明瞭」にしたり「ドラムをバタつかせたり」、あるいは「空間の広がりを濁らせたり」というような悪影響を及ぼすから、この影響を低減するためにウーファー(スピーカーのウーファー、サブウーファーは含まない)を床から30㎝以上離れるように、スピーカーを持ち上げて設置すると空間の濁りや音場の透明度、広がりが大きく改善する。
また、低音は音響エネルギーが大きいので減衰しにくく、スピーカーと周囲の壁との距離の関係がまずいと、簡単に「共鳴」をおこし、低音の一部が減衰せずに持ち上がり、やはり上記と同様の悪影響を与えてしまう。「共鳴」が悪さをしている場合には、スピーカーの位置を数㎝動かすだけでも「共鳴」が消え、嘘のように濁りがとれることがあるから、「スピーカーとその背後の壁との距離」は重要なチェック・ポイントになる。
スピーカーの位置を大きく変更できないとき、あるいは位置を変えても症状が改善されないときには「低音エネルギーの吸収率が高い吸音材」などを用いて低音をスピーカーのすぐ近くで吸収するなどの方法で対処するしかないが、部屋の大きさが6~8畳以上あるか、大音量を常用しない限りそのような問題はあまり生じない。
ソフトの録音の問題
時々、お客様から「このソフトを上手く鳴らしたい」という相談を受ける。そんなときには例外なく「ソフト持参」で3号館にお越し頂くことになる。そして、お客様のソフトを聞いてみると、ほとんど場合ソフトの録音に問題があり、お客様の装置や聴き方に問題があることは希である。では何故そのような問題が生じるかというと、考えられる理由がいくつかある。
オーディオがデジタル化されて久しいが、デジタル化によって「後編集の自由度」が大きく向上したことをリスナーは余り知らない。録音したデジタル信号をパソコンに取り込むことで「1/1000秒以下の単位」で「音を継ぎ接ぎ」できる。これはアナログ編集では考えられなかった高い精度だ。この「時間軸上の高い精度が確立された」ことで「継ぎ目を完全に隠した多点編集」が可能となり、今やスタジオ録音されたソフトで「継ぎ接ぎ編集されないソフトは皆無」と言って差し支えない。
例えばPOPSでは、楽器とボーカルを別々に何度も収録し「一番良さそうな箇所を抜き取ってつなぎ合わせる」ことで「奏者の実力以上のソフト」が生み出されている。そしてこの複雑な編集は、POPSだけに限ったことではなく、クラシックでも同様に「演奏ミスを消し去る」ために多用されている。このような「継ぎ接ぎだらけのソフトの演奏が心に響く」はずはない。BGMとして聞き流すのが精一杯だ。
編集により最も大きな問題を抱えているのが「編成の大きな交響曲」や「室内楽」だ。前述したように、我々は「音の聞き分け」を「高調波と基本波の時間的関係」によって行っているが、設置されたマイクは「楽器からの直接波」だけを捉えているのではないから、複数のマイクで収録した音を重ねると「複数の高調波と基本波の関係がごちゃ混ぜ」になり「楽器の音の認識に大きな悪影響」を及ぼしてしまうのは自明だ。
もちろん、今や「2本のマイクだけでステレオ録音する」なんて野蛮なことは行われていないから(本当はそれが一番音が良いのだが)大なり小なり「音の関係に乱れが生じる」のは仕方がない。しかし、「グラムフォンの3Dや4D録音盤」は明らかにやりすぎで「完全に音楽が破壊」されている。確かに、彼らが想定している「ラジカセやミニコンポ程度の音質」なら、高いレベル(大きな音量)で収録された「高調波」しか再現できないから「高調波と基本波の関係」や「複数の高調波の関係」、もっと単純に言うなら複数のマイクが捉えた音の関係に「大きな矛盾」は生じない。従って彼らの編集は安物(失礼)の装置では大きな問題ではない。
しかし、このようなソフトを高性能な装置で再生すると「各々のマイクが捉えた音像」が「見事にダブって重なって」しまい、リスニングルームには「得体の知れないゴチャゴチャの楽器の集団が出現」することになる。正に「ライブな部屋で音量を上げすぎた時」と同じようになってしまうのだ。このようなディスクは、どのように再生しようとも決して心地よく聞くことは出来ない。唯一の救済方法は、AVアンプで「疑似サラウンド化」して、マルチチャンネル再生することである。そうすると不思議なくらい「音がほぐれて」聞きやすくなり、雰囲気も感じられるようになることがある。
モノラルからサラウンドへ
BBEプロセスの説明に端を発し「高調波と基本波の時間的関係」にこだわって話を進めたが、実はこの関係も「人間の音の聞き分けプロセスの一部分」にすぎない。実際には、もう少し「複雑だが単純な方法」で私たちは音を聞き分けているはずだ。だが「音の聞き分けに最も重要」なのは「時間軸上の精度」であることは間違いないと私は思う。
最高の精度の録音は何かと聞かれたら、私は瞬時に「モノラル」と答える。たった一つのマイクで収録された「音」をフルレンジやあるいは小型2WAyスピーカーのような「矛盾の少ないトランスデューサー」で再現することが「音の精度」のためには理想である。そのようなシステムの再生音が「楽器の生音」に最も高い精度で近い。「演奏者の出した音」を知りたければ、オーディオはモノラルでよいのかも知れない。
しかし、一般的に要求される「客席で聞く雰囲気」を出すためには、スピーカーは一本では少ない。2本でも不十分で、やはり「サラウンド(マルチチャンネル)」を薦めたい。スピーカーの数が増えると、改善されるのは「音場の広がり」や「雰囲気」だけではない。今はまだ何故かはわからないでいるが「楽器の音色の複雑さ」や「アタックの精度」も改善するのだ。複雑になれば「関係は乱れる」はずなのに、サラウンドではその逆の現象が起きる。非常に不思議だが、嬉しい事実であることには間違いがない。
目差すべきもの
つらつらと思いつくままにいろんなことは書いては見たが、かえって皆さんを混乱させただけかも知れない。もしそうなら心からお詫びを申し上げる。私が言いたいのは「CDを聴くなら原音追求ではなく上手に音を作りなさい」ということである。あるいは、機器を買い換えなくても、セッティングを変えたり、ケーブルを変えたり、インシュレーターを変えたり、些細なことでも「音作りは可能」だということだ。 音作りは楽しいが、「音楽を聴く」という目的だけは外さないで欲しい。音作りのための機械いじりがオーディオの目的ではないからだ。ある意味では、オーディオで音楽を聴くのは「小説を読み返す」ことに似ているのかも知れないと時々思う。自分の成長と共にオーディオの音も成長する。昔わからなかったことが、徐々に明確に聞き取れるようになる。結局、「オーディオを楽しむという行為自体」が「心の中に描いた音楽を自分の目の前に実音として出し、自分自身の内面を深く掘り下げること」なのだろう。終わり無き探求。再現無き自己の限界への挑戦。それが、趣味としてのオーディオの本質なのだ。 私のたどり着いた結論でありオーディオのスタートの「お手本」というわけではないが、CD+プリメインアンプで92,000のセットを「LITTLE COSMOS」と名付けて発売した。機会があれば、一度は聴いて欲しい。安くて簡単なコンポだが、大型スピーカーもきちんと鳴らす。そしてなによりもこのコンポは、驚くべきことにCDをまるでレコードのように鳴らしてしまうのだ。案外その音に「オーディオとして目差すべきもの」が集約されているのかも知れない。