究極の純度を目指して…
当初、私は「録音された音を可能な限り正確に元に戻すことが音楽を蘇らせる唯一の方法」と考え、その「究極の純度」を目差して、極限まで音の精度を高める実験を行うことにしました。マイク、マイクアンプ、コネクトケーブル、録音機器など「録音~再生」に関わる全ての機器を市販状態からさらに自分で手を加えて可能な限り高性能化しました。中でもマイクスタンドの不要な振動の低減のためオーディオ用高性能インシュレーターを使用したときのめざましい効果は忘れられません。さらに、音質だけではなく「音の広がり=定位感」を完全に再現するために、収録時のマイクと再生時のスピーカーの位置関係を一致させることを試みました。録音時の左右マイクの距離(幅)とプレイバック時のスピーカーの左右の距離(幅)を同一にすれば、音源までの距離感のズレが少なくなるだろうと考えたのです。
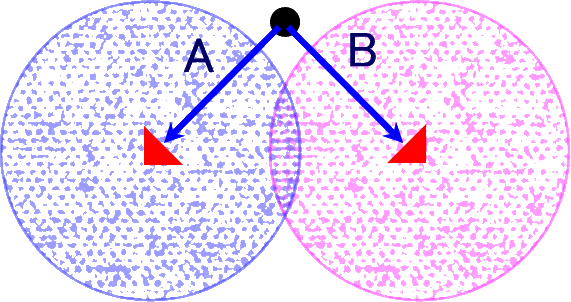 |
 |
| 収録時にマイク(▼)とステージの音源まで距離角度を合わせて収録すると、2本のマイクの捉えた空間情報だけが収録される。 | 再生時にスピーカー(▲)をマイクと同じ幅に設置し、正三角形を描くように精密に角度を調整して再生すると、マイクが捉えたのと同じ空間情報が再現される。(音場がクリア) |
この距離の一致を確実なものにするため、収録時のマイクの幅を約1.8m程度にしてマイクとステージの中央付近から左右マイクまでの距離をメジャーで測って等距離とし、さらにマイクの角度をこのポイントから照射したレーザー光線がマイク(マイクに張り付けた鏡)に当たって正確にポイントに戻るように(マイクのエレメントがポイントに対して正確に正対するように)設置し録音を行いました。再生時にはスピーカーの幅を録音時のマイクの幅と同じにした上でレーザーセッターを使ってスピーカーがリスニングポジションに対して正確な正三角形(2等辺三角形でも問題ないと思います)に位置するように厳密に調整して再生しました。すると驚くべきことにコンサート会場とリスニングルームで聴いている音が「ほぼ完全にイコールになった」と言って差し支えないほど自然で広大な音の広がり(音場空間の一致)とリアリティーが高くかつて経験したことがないほどの正確な楽器の音色の再現(音質の一致)が実現し、コンサートと見まごうばかりの「音楽の再演」が可能となったのです。ところがこの装置で市販ソフトを再生すると「???」期待していたのとは正反対。音楽が全然心地よい良い音で鳴らないのです。音の広がりが不自然で、楽器が重なったように音がぐちゃぐちゃに混ざったり、個々の楽器がてんでバラバラになっているように聞こえます。(それぞれの演奏者が自分勝手に相手のことを考えず演奏しているように聞こえる)まとまりがなくハーモニーも濁り、なんだかうるさくって音楽に集中できないような音なのです。
それは現在行われているレコーディングが収録時に3本以上のマイクを使用し、それぞれのマイクの信号を専用のトラックに収録した後、それらをミキシングすることで作られていることと無関係ではありません。このような録音はマルチマイク(マルチトラック)録音と呼ばれています。この方式では、録音しようとするコンサートをいくつかのパーツ(部品)に分け、個々のパーツを他のパーツと干渉しないように、専用のマイクとレコーディングトラックで収録します。なぜなら、「演奏」は常に完璧なものとは限らず「現場での収録」も同じなので、このように一つの音楽(演奏)をいくつかのパーツに分けて録音しておけば、後日一部のトラックの音量を調整して特定の楽器(ボーカル)の音の大きさを変えたり、場合によっては「ミス」した部分だけを演奏し直して差し替えるなど、最終段階での音作り(音楽を傷のない商品に変える、もっと魅力的な音にする=マスタリング)時の「切り取ったり」、「張り付けたり」、「入れ替えたり」という作業が非常にやりやすくなるのです。特に音源がデジタル化されてからは編集機の機能と性能が飛躍的に高まり、アナログ時代に比べマイクと収録トラックの数は数倍以上に増えています。
しかし、非常に上手く編集されたソフトであってもオーディオマニアが使うような異常に性能の高い装置(一般的ではないという意味で)で聴けば、レコーディングエンジニアが意図しなかったほどの(ほぼ目立たなくしたはずの)編集時の欠点が克明に再現され、まるでゴーストだらけのTVを観ているように音場が歪んだり、音が濁ったすることがあるのです。つまり、性能の低い装置では「マイクの捉えた直接音」しか再現しないため、「重なりの濁り」が表面化しないのですが、性能の高い装置では、本来聞こえてはいけないはずの「マイクの捉えた間接音(マイク周辺の空間情報)」まで再現され、それが仇となって先に述べたようなゴースト問題が生じてしまうのです。
 |
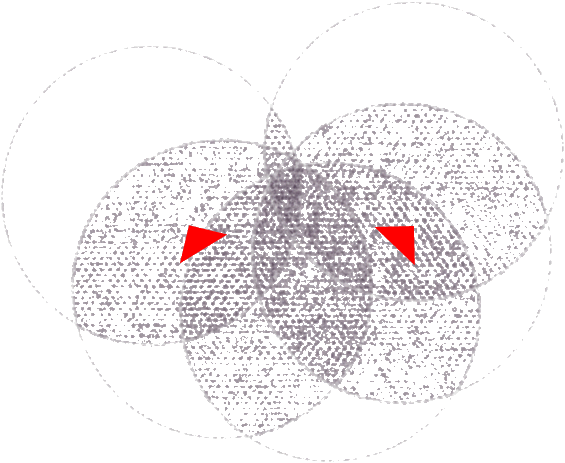 |
| 収録時にランダムに設置した多数のマイク(▼)を使用すると、それぞれのマイクが捉えた空間情報も収録される。 | 再生時に2本のスピーカー(▲)だけを使用しても、マイクが捉えたそれぞれの空間情報が再現され、「多重」になって再現されてしまう。(音場が濁る) |
CDの音質がマスターに比べて著しく劣化している
もちろん、この問題の対策のため各パーツの音を完全に他のパーツから遮断すべく演奏者を独立したブースに入れて収録したり、指向性の強いマイクで録音を行ったり、超精密な編集機器(プロツールスという編集機が業界標準)で仕上げの作業を行うなど、欠点を「極力目立たなくする努力」は行われています。しかし、残念ながらすべてのソフトを「最高水準で仕上げる」ためには、商業的にコストが許されないため市販ソフトには問題が残されたものが多いようです。さらに残念なのは、マスタリングであまりにも多重ダビングを繰り返すためか、販売段階でのCDの音質がマスターに比べて著しく劣化していることです。
結局、オーディオマニアの一般的な認識とはまるで逆に再生装置の「物理的な精度」を高めれば高まるほど(音をよくすればよくするほど)マイクの位置の不整合、ミキシング時の音量調整の未熟さや各パートの整合性の低さ・・・、数え上げればきりがないほどの「ソフトの粗(録音の問題)」が明確になり、さらにそれを何とかクリアしても、今度はスピーカーの位置のズレ、その日の温度や湿度による音の違い、電源による音の違い・・・、といったいわゆる再生時の環境の問題が発現するなど様々な問題が気になってとても音楽に集中できる状態ではなくなるのです。この状況を例えて説明するなら、白い紙の上の小さなゴミを見つけるようなものです。装置の精度を上げることはすなわち「紙を白くすること」。問題を解決すると言うことは「目立っている大きなゴミを拾う」ということです。「紙は白いほどゴミが目立ち=装置の性能は高ければ高いほど問題は露呈しやすく」さらに「大きなゴミを拾えばそれまで目立たなかった小さなゴミが気になる=問題を解決すれば別の問題が露呈する」ということになります。繰り返しになりますが、装置の物理的な性能が向上すればするほど、それ以前は目立たなかった問題が表面化し、それをクリアすると、また隠れていた別の問題が浮かび上がる。それを解決しても・・・とその繰り返しが続くばかりで永遠に安心して音楽を聴けるようには鳴らないのです。やり方がまずかったのかも知れませんが、「再生装置の精度を高めるのは焼け石に水」それが私がたどり着いた「原音追求」の結末です。 この経験を踏まえ私は、ソフトに収録された音楽は「破壊されている=仮死状態になっている」と仮定し、再生時に再び生命を与える(蘇生させる)べきではないか?と考えています。(以下次号に続く)
